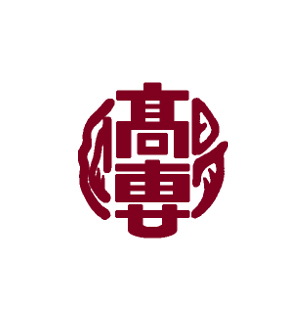 web版高専だよりNo.10 教員の研究紹介
web版高専だよりNo.10 教員の研究紹介
- 2022年03月31日
- 高専だより特集記事
今回は、藤崎先生の研究を紹介します。
○一般教育科 藤崎 祐二 先生
私の専門は上代日本文学です。上代というと聞き慣れない人も多いかもしれませんが、奈良時代に相当する時代区分です。現存する最古の文献資料が奈良時代初頭に成立したとされる『古事記』ですので、まさに黎明期の日本文学を扱うこととなります。『古事記』以外には、『風土記』『日本書紀』『万葉集』などが現存しています。
この時代はまだ平仮名が発明されていなかったため、文章を書く際には漢字が用いられました。
しかし、漢字一つをとっても対応する日本語が複数あり、さまざまな読み方が可能であるため、執筆者が意図したとおりに読むことは容易ではありません。『古事記』をはじめとする上代の文献資料は、これまでの研究成果の蓄積によって訓読され、多くの現代語訳も行われてきましたが、細かい表現に目を向けるならば、まだまだ再考の余地があります。そこで私は、漢字一つ一つを俎上に載せて、現行の解釈が妥当なのかを検証し、執筆者の意図を明らかにする作業に取り組んでいます。
その中で現在は、特に託宣の場面などに見られる憑依表現に注目しています。上代においては、神々と人間との関わりが重要な意味を持っていたため、文献資料にも憑依を伴う託宣の場面が多く描かれています。憑依表現を研究することで、同時代の思想や精神性を明らかにするための手がかりが、得られるかもしれません。また、このような神々と人間との関わり合いは、上代のみならず現代にいたるまで、あらゆる文献資料に散見されます。時代ごとの憑依表象の変遷に着目することは、「人間とは何か」という永遠の課題と向き合う上でも、有意義であると考えます。
以上のような問題意識を持って研究を進めていますので、上代だけでなくさまざまな時代の文献資料に目を通し、比較しなければなりません。また、時代ごとの相違だけでなく、ジャンルごとの相違に着目する視点も重要になるでしょう。例えば、日記に記録された憑依は実体験に基づいているのに対し、物語に描かれた憑依は作者による創作ですから、両者を同次元で扱うわけにはいかないわけです。
さて、やるべきことは山積みですが、新しい発見を夢見て、日々の研究に従事しております。